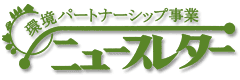
|
第12号
平成16年9月27日 発行 |
|
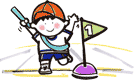 暑く台風の被害に見舞われた夏も過ぎ、秋の気配を感じるこの頃、みなさまいかがお過ごしでしょうか。 暑く台風の被害に見舞われた夏も過ぎ、秋の気配を感じるこの頃、みなさまいかがお過ごしでしょうか。
さて、第12号のニュースレターができましたのでお送りします。今後の活動の参考にしていただければ幸いです。
 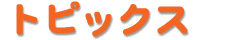
  環境月間中の6月19日(土)に開催された「おかやま生きものシンポジウム」を取材しました 環境月間中の6月19日(土)に開催された「おかやま生きものシンポジウム」を取材しました
岡山の多様な生き物と私たちが
共生するまちづくりを!
非常に分かりやすい興味のある具体的な報告をたくさん聞くことができました。そして私たちは自然保護や環境保全は人間以外の動植物のためだとか農家の問題とだけ思っていましたが、実は自分自身がその当事者でありしかも受益者であったのです。
 人間にとって…害虫、益虫、ただの虫 人間にとって…害虫、益虫、ただの虫
宇根 豊さんの話で、印象に残ったのは次の話です。稲の根元に板をあてて稲をたたくと、板の上にたくさんの虫が落ちてきます。うごめく虫とじっとしている虫のどちらが害虫かと問われても、農業経験のない人は、すぐには答えられません。じっとしている虫が害虫なのです。
ただの虫というのは、害にも利益にもならない虫のことですが、例えばユスリカなどをいいます。これは稲とか野菜にとって"ただの虫"ですが、稲に有益なツバメやトンボの大切なエサになります。これを農薬や休耕田にすることによって繁殖をとめると、こうした益鳥や益虫をピンチにおいこみます。
 休耕田の蛙 休耕田の蛙
夏の風物詩である田んぼの蛙の合唱は、苗代のために田んぼに水を入れないと始まらないそうです。隣の田んぼに水が入ってもそこへ浮気に行くことなく、自分の住んでいる田んぼに水が入るまで待っているそうです。
 鮒飯の話 鮒飯の話
萩原市長は、年に一回有志で集まって鮒飯を作って食べるのが恒例とのことです。安心して鮒飯が食べられる岡山の川に感謝している、そして、その川の水によって作られる米が安全であることをPRするべきと話しておられました。スイゲンゼニタナゴや鮒がそこの米の安全を保証しているという具体例です。
 ギフチョウと林道の整備 ギフチョウと林道の整備
ギフチョウ保護の発表もありました。休みの日に県北をドライブするとしたたるような緑に心がいやされます。山奥まで整備されているので実に快適です。しかし、それと引き換えにギフチョウの幼虫が食べるアオイ科の植物が消えてしまっているのです。ギフチョウの身になってみると胸塞がれるおもいです。
これが今回の私の報告です。(市民環境記者 広坂)
| ※シンポジウムの報告書をご入り用の方は、環境調整課までお申し付けください。 |
|